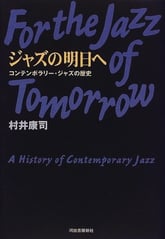
歴史が何故重要か。歴史は物語であり、それを編んだ「時点」での意識(対象が政治であれば政治意識)を体現したものである。だから古事記は日本が歴史時代に突入した時点での政治意識を著した古代史・神代史であることは自明だし、隣国との歴史問題は、「過去の事実に関する論争」ではなく、本質は「現在の政治意識」のもとでの闘争である、と理解しなくてはいけない。
だからジャズに歴史問題があるならば、それは「過去の事実」のことでなく、「過去の事実に対する現在の認識論」なのだ。現時点での意識の座標軸を同定したうえで、過去をファイリングし・語り、未来を眺め・目指す。まず、そのことを自分自身でよく認識せねばならない。
柳樂光隆さんのジャズ本を「チラ読み」したときの言葉にできない違和感があって、それを書きたいと思った。だけど、言葉にできないので、言葉にするために、もう少し考えなきゃいけない、と思った。熱心じゃない時間が長いのだけど、35年もジャズを聴いていたのだから。間違いなく、ボクに一番寄り添ってきた「なにか」だ。
そんな訳でジャズ本を集中読書中。この村井康司さんの「ジャズの明日へ」は20世紀のお仕舞いに書かれた、ということで意味がある本だと思う。ボクら(村井さんは2つ上だから同世代に含めても良いと思う)にとって、21世紀は未来と同義語で、20世紀のいろいろなことが止揚された「明るい未来」の筈「だった」。だから、20世紀のお仕舞いになって急速に視界不良になったジャズへの想い、のようなものが感覚的によく分かるのだ。これも歴史認識なのだから、認識の担い手がリアルタイムに感じたことが「リアルな歴史」であって、伝え聞いた、あるいは読み知ったことは「神話」に近い。この手の議論に、書き手の座標軸(時間軸)を明確に打ち込まなきゃいけない。確かに、ボクらにとって、1970年あたりが境界となって(著者的には1967年)、それ以前が「幸福なジャズの神話時代」、それ以降が「歴史時代」なのだ。
この本は、1970年以降のジャズ(ボクらの歴史時代)を俯瞰的にまとめた好著。全く違和感はなくて、いい加減なリスナであるボクの落とし物を丁寧に拾ってくれる。ディスクガイドとしても秀逸だと思う(同時期の好著:200CD 21世紀へのジャズ/立風書房も読むべし。同じ世界観)。1967年をもって、ジャズの巨人達が睥睨し綴られた神話のページが閉じられ、分散されていった「軽いコンテクスト」を纏ったジャズが広がっていく様子。マイルス存命のうちは、「神話時代のふり」をして、同じようなフレームワークで語られていたように思える。彼は、それを再構築し、すでに1967年から神話は解体されていった様子が良く理解できる。1960年代末からのソウルなんかを、ぼんやり聴いていると、ジャズが相対化される部分があって、極論すると1970年代のジャズって「後進的だったリズムの幅を取り戻した」だけ、って感覚があったのだけど、そこのトコロを上手く書いていると思った。こうして書いているのも、彼の本を触媒に思考しているからだ。
さてこの本が書かれた20世紀の最終年で、確かな座標軸が与えられ、未来をみているのか。しかるに、この本も(ボクの意識と同じく)マイルスの死で視界不良となったところで終わっている。やはり、と愕然。同世代なので、時代意識(のようなもの)が共有されているとまさしく実感した。このメモの冒頭で、歴史、ということの定義を書いたのは、このため。気がついた。
村井さんの近刊(ディスクガイド)もとても好きな本なのだけど、この20年のディスクの少なさは、やはり、の感覚。いよいよ、「柳樂光隆さんのジャズ本」をもう少しきちんと読むのだけど、グラスパーっていいのだけど、中心に据えること自体、模擬的に「神話の時代」をなぞっているような居心地の悪さ、はある。ようやく、読むにあたっての、自分の座標軸はおぼろげにできた。
村井本での世代共有感が案外重要で、「あの本」にはそれによるシンパシーが全くない、という負のバイアスがあるのは確か。それは、自分自身、承知しなきゃいけない。
ジャズシーンが、ジャズ批評の今月号のような「マイ・ベスト・ジャズアルバム」のような世界(みんな驚くほどバラバラ)であるならば、そのなかで自分の嗜好をどのような座標軸で捉えるか、だけのことなんだろうな。絶対座標系の神話の時代はとっくに終わったのだから。